神仏習合とは、古来より日本にある神様を祀る神道と、インド発祥の中国、朝鮮半島を経由して渡来した仏教の思想が、互いに影響し融合したことを言いあらわします。明治時代になると神仏判然令が出され神仏分離がなされ現代にいたります。
ここでは、「神社検定テキスト 神社のいろは」第3章㉒仏教が神社に及ぼした影響について教えてくださいのページの内容を掘り下げて学習し、暗記しやすいようにスマホでも見やすい1ページにまとめてみました。
神仏習合
日本に仏教が伝わったのは、6世紀中期頃(550年前後)です。
仏教が渡来すると「外国の神」として受け入れられ、徐々に広がっていきました。

当時の朝廷では、仏教の受け入れについての対立もありました。
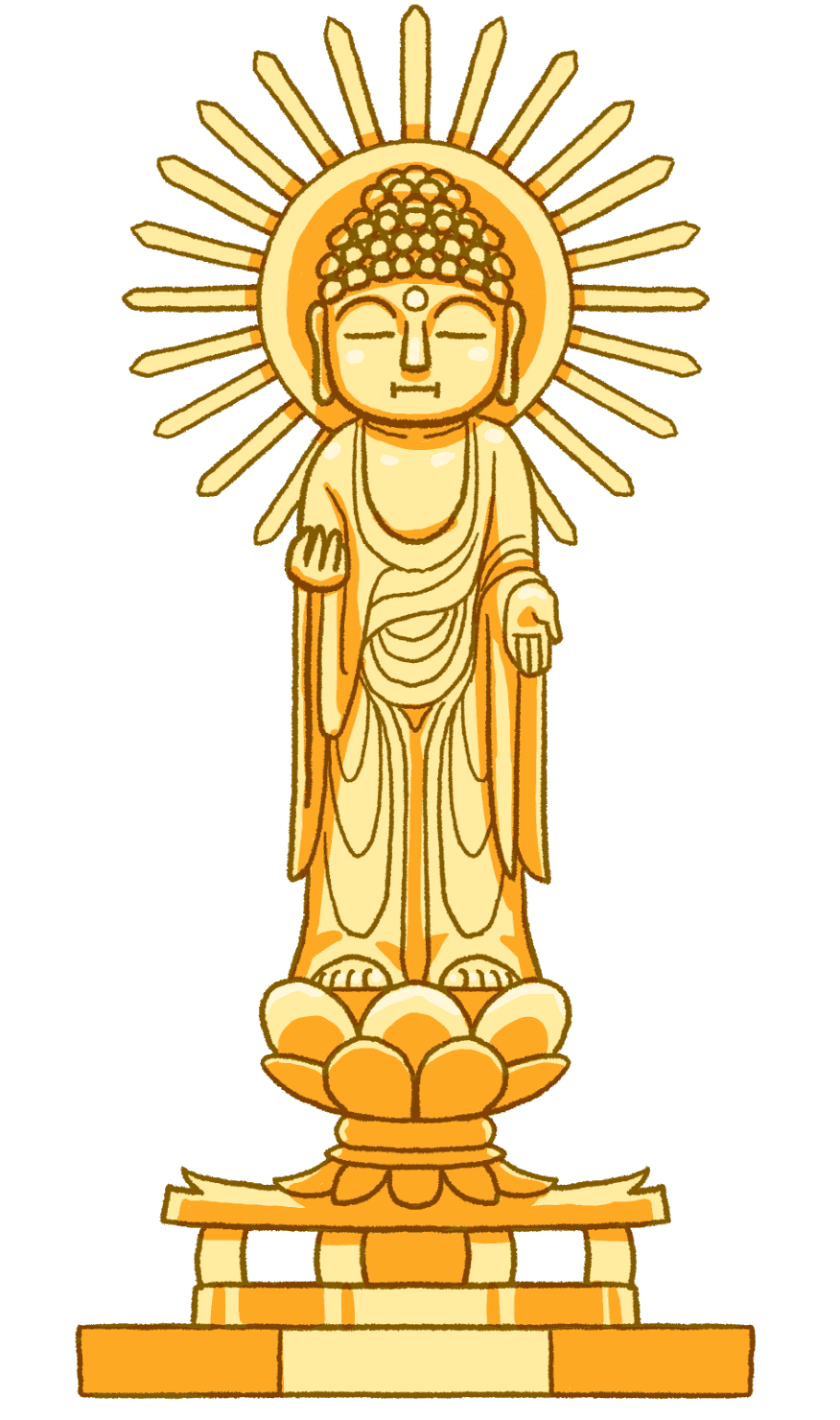
①神宮寺 (じんぐうじ)
仏教が広まると今度は仏教関係者は、日本古来からの神々との関係性をどのようにとらえたらよいのか考えていきました。
奈良時代には、神々を輪廻から救い出さなければならないという考えら神社の境内には、日本の神々を救う神宮寺が建てられる例ができました。
又、寺院の境内では、インドの神々は仏法を守る存在であるということから、寺院の境内や近所に神社を勧請(分祀、お遷し)する例がでてきました。

②本地垂迹説 (ほんじすいじゃくせつ)
平安時代になると、仏こそが真の神の姿である「本地」であり日本の神々は人々を救済するために仮の姿で現れた「垂迹」と考えられました。
この説により「神は仏と同体=神仏習合」と考えられました。
熊野神の本地(真の姿)は阿弥陀如来とされ、春日神は不空羂索観音とされました。
熊野権現は、仏が仮に神の姿をして現れるということから、新たな神様の称号「神号」になりました。
③宮寺
日本の神々は、本来は山などの自然のものに依りつくと考えられていましたが、奈良時代には仏教文化の影響を受けて「神像」を作る例もでてきました。
神社の御本殿には「神像」や「仏像」が安置され、境内に寺院を建てて僧侶と神職が並んで祭祀を管理する例もでてきました。これを「宮寺」といいます。

祭祀に関しては神職は神式で、僧侶は仏式で行われていました。
④神本仏迹説 (しんほんぶつじゃくせつ)
鎌倉時代には「神本仏迹説」がでてきます。神こそが仏の真の姿であり、仏は神の仮の姿であるという考え方です。
この後儒教などの影響もうけ、江戸時代までに様々な様々な考え方に派生していきます。
⑤修験道(しゅげんどう)
修験道は、仏教や道教、陰陽道の影響を受けて成立しました。
神々がいるとされる聖地の山で、様々な厳しい修行をして超越的な力を身に付け広く人々の救済をしようとするのが修験道の修験者(山伏)です。
平安時代になると、真言宗や天台宗によって山々に寺院が設けられ山岳霊場が増えます。
奈良の吉野、和歌山の熊野、山形の出羽三山、福岡の英彦山などが有名な山岳霊場です。
神仏分離
明治時代には、明治政府によって神仏判然令が廃止されます。

江戸時代の中頃に、国学思想の影響を受けたためです。
⑥神仏判然令(しんぶつはんぜんれい)
神仏判然令は、仏教風の神号の廃止(神号の廃止)や神社に設置された仏像や仏塔を除去し、仏像や宮寺を打ち壊すなど過激な廃仏毀釈が行われるなど過激な混乱もおきました。
こうして神社では仏的要素が取り除かれ、寺院などでは神道的要素が取り除かれて神仏分離がなされました。その後、修験道も廃止されました。


コメント