 神馬とは、古代より神様の使者や乗り物として崇められ、日本の神社文化に深く根付いた存在です。全国の神社には、生きた神馬が祀られている場所があり、東京でも神馬のいる神社を訪れることができます。
神馬とは、古代より神様の使者や乗り物として崇められ、日本の神社文化に深く根付いた存在です。全国の神社には、生きた神馬が祀られている場所があり、東京でも神馬のいる神社を訪れることができます。
白馬の神馬や、伊勢神宮で皇室から献上された神馬など、神聖でスピリチュアルな雰囲気を持つ神馬は、多くの参拝者を魅了しています。また、神社で見られる馬の像や、競走馬として活躍したサラブレッドが神馬として新たな役割を果たす例もあり、その存在は多様な文化的背景を持っています。
神馬を通じて、日本の伝統やスピリチュアルな世界観に触れる旅へと出かけてみませんか。
- 神馬は神様の使者や乗り物として信仰されている存在
- 日本各地の神社に生きた神馬やその像が存在する
- 伊勢神宮の神馬は皇室から献上された特別な存在である
- 神馬は地域の伝統行事や自然信仰に深く結びついている
神馬とは?由来と魅力を解説

- 神馬のいる神社 東京で訪れるべき場所
- 生きている神馬のいる神社
- 伊勢神宮の神馬の特別な存在
- 神社で見る馬の像の意味は?
神馬のいる神社 東京で訪れるべき場所

東京で生きた神馬に会える神社は、都市部ありながら歴史や伝統を感じられる特別な場所です。
神田明神
神田明神は、東京の中心部、御茶ノ水駅から徒歩圏内に位置する神社です。この神社では「神幸号(みゆきごう)」と呼ばれるポニーの神馬がお迎えします。愛称は「あかりちゃん」で、境内で散歩する姿は多くの参拝者に親しまれています。神馬を見るだけでなく、神社の歴史にも触れることができます。劇場版アニメ「ラブライブ! The School Idol Movie」の中で登場しています。
日光東照宮
東京から少し足を延ばせば大丈夫、栃木県の日光東照宮にも訪れることができます。 この神社にはニュージーランドから奉納された白馬「光丸号」がいます。 外国から奉納された神馬は全国でも非常に珍しいですね。「福勇(ふくいさみ)号」の後継、「晃白(こうはく)号」が仲間入りしました。
生きている神馬のいる神社

日本の神社には古来から、神聖な儀式や神事に「白馬」が登場する伝統があります。 白馬は特別な存在とされ、神様が乗る神馬として信仰されてきました。いくつか紹介します
【伊勢神宮】三重県
神宮の神馬は皇室から献上され、内宮と下宮の御厩にいます。
神馬さんは、毎月1.11.21日の8時頃に正宮にお参りします。雨天や神馬さんの体調によっては中止されます。
【神田明神】東京都

拝殿右奥の神幸号というあし毛の神馬さん(ポニー)がいます。
愛称は「あかりちゃん」で、明るく平和な世を願い、神田明神様の明の字を頂いたとのことです。
【多度大社】三重県

白馬伝説の残る多度大社では、神馬舎に神馬さんがいます。
「多度大社神馬会」があり、活発に活動しています。

【日光東照宮】栃木県


初代の神馬さんは、家康公が関ヶ原の戦いで乗った白馬で神馬の碑があります。
外国から奉納された神馬さんは、ニュージーランドの先住民族のマオリ語で「守られている」という意味の「コーマル」から名前は光丸号です。

【上賀茂神社】京都市


神山号はサラブレッドで、かつてJRAで競走馬「メダイヨン」として活躍した神馬さんです。
日曜祝祭日と、神社の祭典日に出社するそうです。



【鹿児島神宮】鹿児島市


清嵐号という神馬さんがいます。葦
毛のサラブレッドで誘導馬をしていたそうです。
【吉川八幡神社】大阪府
いづめ号は日本馬で川原毛という貴重種の神馬さん。
令和元年の改元と新天皇御即位に際し2019年6月に御神馬として来られたそう
【相馬中村神社】福島県


ミニチュアホースと引退したサラブレッドがたくさんいます。
馬場と厩舎がありNPOの方が飼育しています。
御朱印も馬、手水舎も龍ではなく馬がいます。
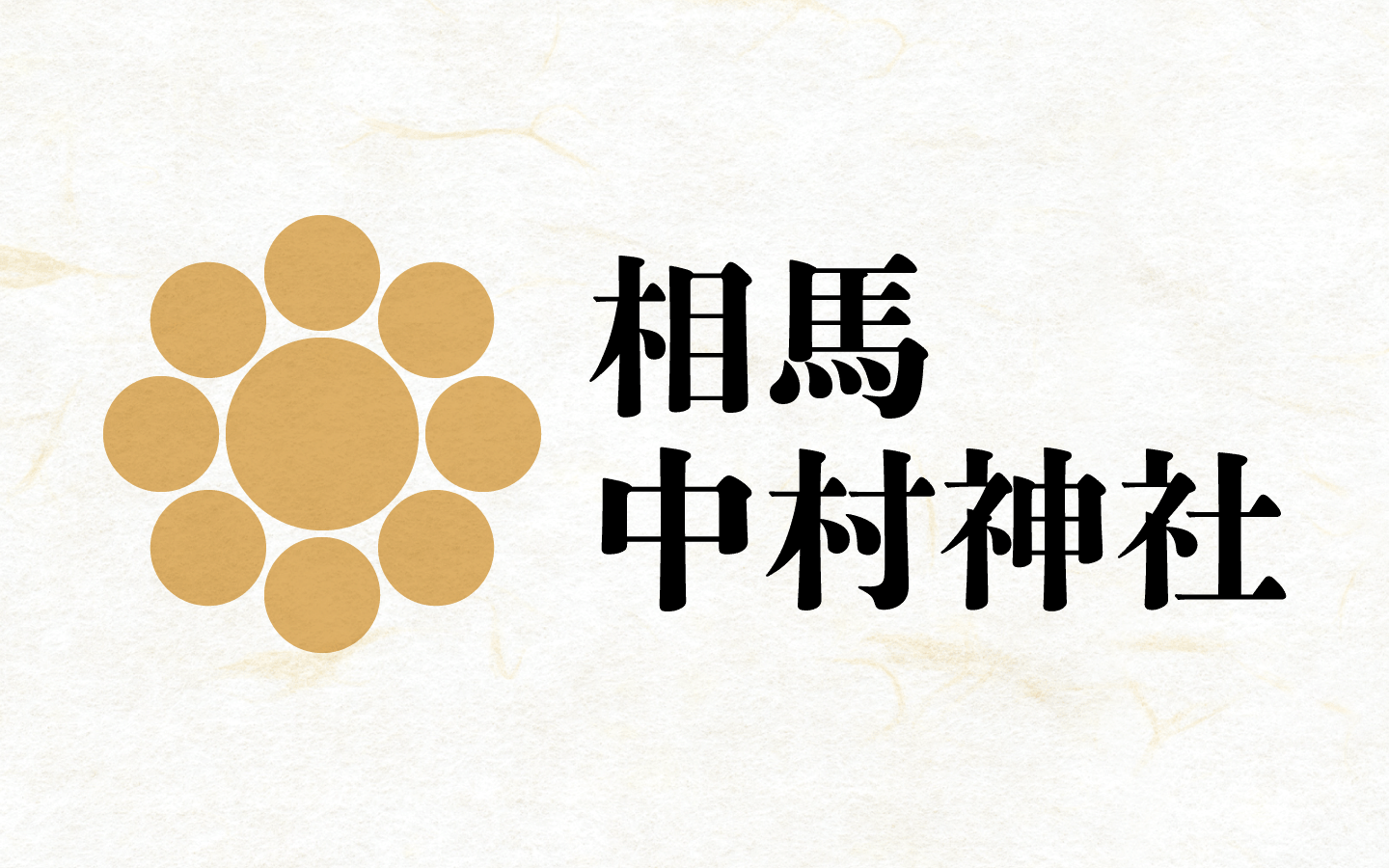

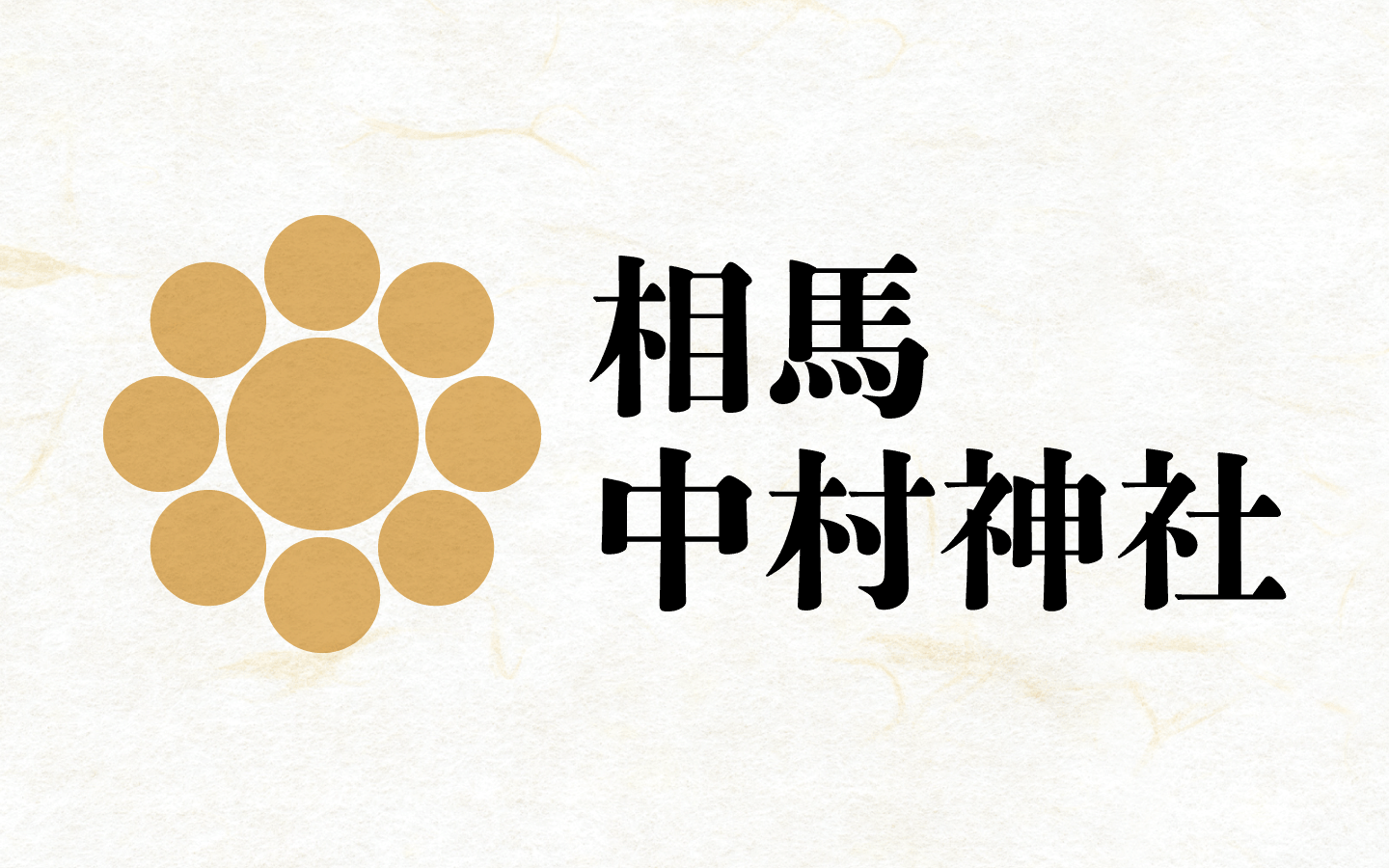
【金刀比羅宮】(重要文化財)香川県


ルーチェ号がいます。他にも流鏑馬に出る馬が複数います。

【大和国鹿島香取本宮】
白馬の鹿島号と香取号がいます。七五三では神馬さんと写真撮影ができます。

【丹生川上神社下社】


丹生川上神社は神武天皇の時代から祭祀(祈雨)を行う重要な場所です。
天平宝字7年(763年)に、黒毛の馬を献上して以来、雨乞いには黒馬(黒龍)、晴れを乞うときには白馬(白龍)を献上するようになりました。
絵馬の発祥の地とされています。現在の神馬さんは白馬と黒馬です。

神馬 伊勢神宮の特別な存在
伊勢神宮は日本の神道文化の中心的な場所であり、その神聖さを象徴する存在として「神馬」が重要な役割を担っています。伊勢神宮の神馬には特別な由来と特徴があり、参拝者にとってその姿は一見の価値があります。
皇室から献上される由緒ある神馬
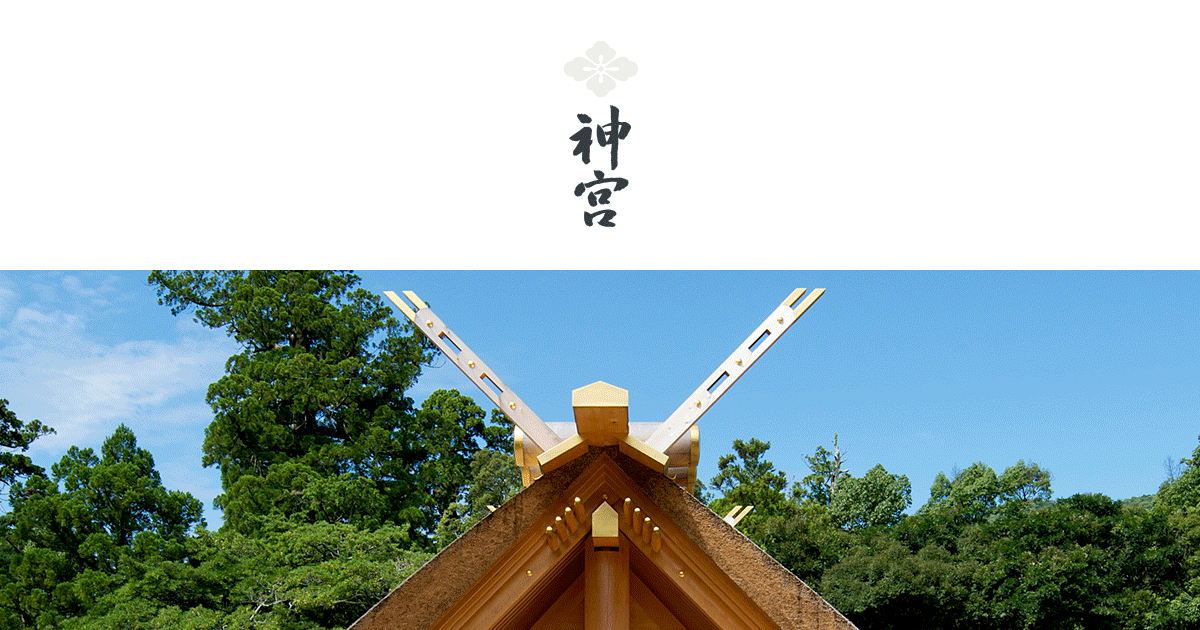

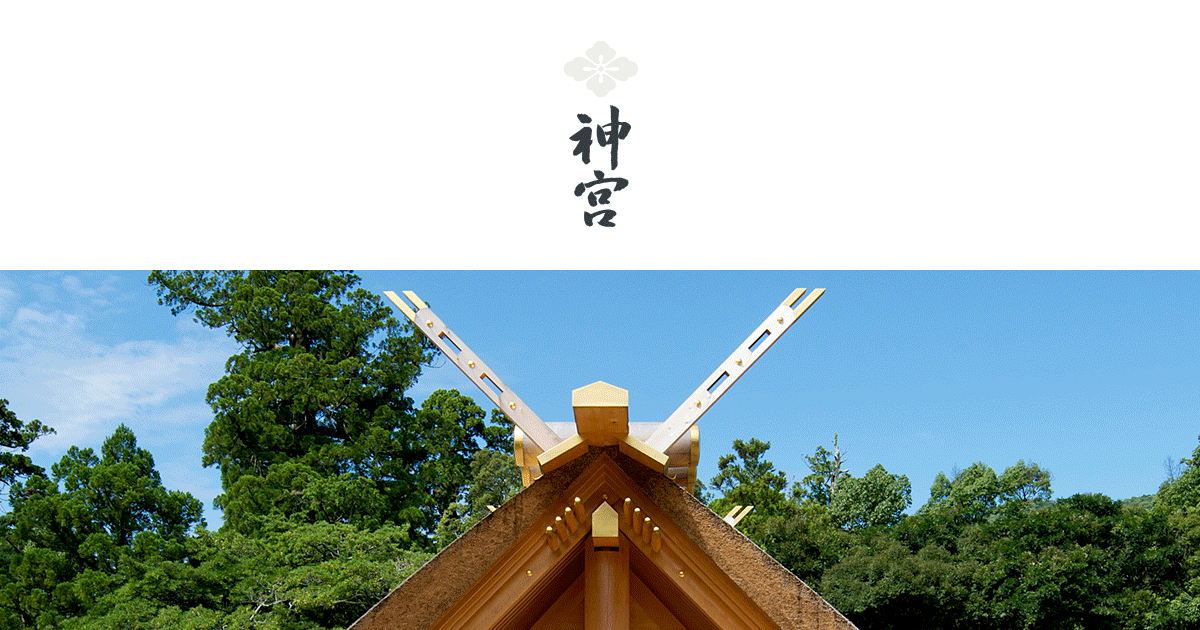
伊勢神宮の神馬は、皇室の御料牧場で育てられた馬が献上され、御馬牽進(みうまけんしん)式が執り行われます。これにより、神宮の神馬は日本の伝統や格式を象徴する特別な存在となっています。
現在、内宮には草新(くさしん)号と本勇(もといさむ)号、外宮には草音(くさおと)号と笑智(えみとも)号の4頭が飼育されています。それぞれの名前には神聖な意味が込められており、その存在自体が神宮の厳かさを際立たせています。
月に3回行われる「神馬の出仕」


伊勢神宮の神馬は、毎月1日、11日、21日に「神馬の出仕」と呼ばれる儀式で正宮に参拝します。この儀式では、厳かな雰囲気の中、神馬がゆっくりと境内を進む姿を見ることができます。
参拝者にとって、この神聖な儀式は日本の伝統文化を間近で体感できる貴重な機会です。なお、天候や神馬の体調によって中止されることもあります。
神馬は単なる動物ではなく、神様の使者や乗り物として特別視されています。そのため、伊勢神宮にいる神馬は神聖さの象徴とされ、清らかで厳粛なイメージを参拝者に与えています。
また、神馬の飼育は専門的な職員によって細やかに管理されており、その手厚い扱いが伊勢神宮の伝統をさらに支えています。
伊勢神宮で神馬を見る価値
伊勢神宮の神馬は、日本の歴史や文化を深く知るうえで欠かせない存在です。その姿はただ美しいだけでなく、皇室とのつながりや古代から続く神道の信仰を感じさせてくれます。
参拝の際には、神馬に目を向け、その背景にある意味を考えることで、より深い参拝体験が得られるでしょう。
神社で見る馬の像の意味は?


神社で見られる馬の像には、日本の古代信仰や神道の文化が色濃く反映されています。
神様の乗り物としての象徴
馬の像は、神様が乗る神聖な存在「神馬(しんめ)」を象徴しています。 古来、馬は神様の使いや乗り物として崇められ、神聖視されてきました。た馬を奉納することが難しい場合、代わりに馬の像が奉納されるようになりました。これが現代の馬の像の起源とされています。
雨乞いや晴天祈願との関連
馬の像には、天候に関する祈願の役割もあります。例えば、黒い馬は雨乞いの象徴として、白い馬は晴れを祈る際に使用されました。神社の馬のイメージを通して、当時の人々が自然との調和を大切にしていた事を感じることができます。
絵馬とのつながり
馬の像は絵馬の起源とも深い関係があります。元々は生きた馬を奉納して神様に祈願していましたが、やがて木彫りの馬や絵に描かれた馬に代わっていきました。の絵馬も、この伝統の延長あるものです。
災害を予防する存在
馬の像には、参拝者を守護し、災いを寄せない役割もあります。神社の境内や入口に設置されていることが多く、その姿勢や装飾には、神社ごとの独自の意味が込められています。
神社で馬の像を見ることは、ただの観賞ではなく、その背景にある日本の信仰や歴史に触れる貴重な機会でもあります。
神馬サラブレッドが活躍する神社


- 神馬のいる神社で体感する伝統文化
- 日本各地の神馬の伝統
- 神馬とともに守られる神社の歴史
- 絵馬の由来と神馬のつながり
神馬のいる神社で体感する伝統文化


神馬がいる神社は、日本の伝統文化を深く感じられる特別な場所です。神馬が果たしている役割やその存在は、古代から現代に至るまで続く信仰と結びついています。これらの神社では、神馬と共に伝統文化を体感することができます。
神馬が果たす神事での役割
神馬は、神様の使者や乗り物とされ、重要な神事に欠かせない存在です。多くの神社では、神馬が参列する儀式が行われており、その厳粛な雰囲気を身近に感じられます。例えば、伊勢神宮では「神馬の出仕」という儀式で、神馬が参拝者の目の前を進む姿を見ることができます。このような儀式を通して、古来の伝統文化を実感できます。
伝統行事と神馬の深い関わり
神馬が登場する伝統行事には、地域の風習や信仰が色濃く反映されています。例えば、奈良県の丹生川上神社では、雨乞いや晴天祈願の儀式に黒馬と白馬が用いられます。また、東京都の立石熊野神社では、七五三などの特別な行事で神馬が子どもたちを乗せ、祈願する役割を担います。これらの行事に参加することで、日本の文化や信仰の奥深さを感じることができるでしょう。
神馬と共に守られる神社の歴史
神馬を持つ神社では、地域の人々が長年にわたって神馬を守り、支えてきました。多度大社(三重県)には、神馬会という組織が存在し、全国の会員が神馬の飼育や維持を支援しています。このように、神馬は単なる象徴ではなく、地域文化の維持や継承にも大きな役割を果たしています。
神馬を通じて感じる自然とのつながり
神馬のいる神社では、神馬の姿を通じて自然とのつながりを意識させられることも特徴です。雨乞いや晴れ祈願といった行事に神馬が参加することは、農耕文化と信仰が一体となった日本の伝統を思い起こさせます。自然と共存し、感謝する心が神馬の存在を通じて伝えられているのです。
神馬のいる神社を訪れることは、単に観光するだけではなく、歴史や伝統文化を体感する特別な機会です。神馬を通じて、日本の信仰や文化に触れてみてはいかがでしょうか。
日本各地の神馬の伝統


日本各地の神社には、古来より神馬が神聖な存在として奉納され、さまざまな伝統が受け継がれています。神馬は地域ごとに異なる役割や特徴を持ち、その土地ならではの文化や信仰が色濃く反映されています。
雨乞いや晴れ祈願の神馬
奈良県の丹生川上神社では、黒馬と白馬が雨乞いや晴天祈願の象徴として用いられています。黒馬は雨を呼び、白馬は晴れを願う儀式に登場します。この風習は古代から続いており、農耕文化が深く根付いた日本独特の信仰を物語っています。
神事で活躍する神馬
伊勢神宮(三重県)の神馬は、毎月決まった日に「神馬の出仕」として正宮へ参拝します。皇室から献上された由緒ある神馬が、厳かな儀式に登場することで、神宮の格式をさらに高めています。また、多度大社(三重県)では、神馬の名前を冠した競馬が開催されるなど、現代的な文化とも融合しています。
地域行事と結びつく神馬
神馬は、地域の伝統行事にも深く関わっています。東京都の立石熊野神社では、幼稚園の園児たちが神馬と触れ合い、神馬が七五三の子どもたちを乗せる行事も行われます。また、山梨県の小室浅間神社では、流鏑馬に神馬が登場し、足跡で吉凶を占う独自の儀式が伝えられています。
地域住民による神馬の保護
多くの神社では、地域の住民や団体が神馬の世話や活動を支えています。例えば、多度大社の神馬会は、全国の会員が参加し、神馬の飼育や維持をサポートしています。このように、神馬は神社だけでなく、地域の文化やコミュニティを象徴する存在でもあります。
神馬と日本文化のつながり
神馬は神様の使者としてだけでなく、日本人の自然信仰や地域の風習とも密接に結びついています。それぞれの神社で受け継がれる伝統は、神馬を中心に地域の歴史や文化を伝える重要な役割を果たしています。
日本各地の神馬の伝統に触れることで、その土地独自の文化や信仰を深く知ることができます。訪れた際には、神馬の姿だけでなく、その背景にある歴史や習わしにも目を向けてみてはいかがでしょうか。
神馬とともに守られる神社の歴史


日本の神社における神馬は、神様への信仰と地域文化の象徴として、長い歴史の中で大切に守られてきました。神馬は単なる動物ではなく、神社の神聖な存在とともにその歴史を紡いでいます。
神馬の起源と神社の役割
神馬は古代より「神様の乗り物」として崇められてきました。当時、馬は農耕や移動手段としても重要な役割を果たしていましたが、神馬はそれ以上に特別な存在とされ、神事や儀式に欠かせないものとされてきました。このような背景が、神社に神馬が奉納される文化を生み出しました。
地域で支えられる神馬
多くの神社では、地域の人々が神馬を守り、伝統を受け継いでいます。三重県の多度大社には、神馬会という組織があり、会員が協力して神馬の飼育や健康管理を行っています。このような取り組みは、神馬が地域にとって重要な存在であることを示しています。
歴史を感じさせる神事と神馬
奈良県の丹生川上神社では、黒馬と白馬が古くから雨乞いや晴天祈願の神事で活躍しています。この伝統は、農耕文化と神社が密接に結びついていたことを物語っています。また、伊勢神宮では皇室から献上された神馬が、毎月の儀式に参列することで、その格式と歴史の重みを感じることができます。
現代に息づく神馬と神社のつながり
競走馬として活躍したサラブレッドが神馬として奉納される例もあります。京都市の上賀茂神社では、かつてJRAで活躍したサラブレッドが神馬として神事に参加しています。このような形で、現代の文化と伝統が融合しながら受け継がれています。
神馬を通じて知る神社の歴史
神馬はその神社の歴史を象徴する存在であり、同時に地域の信仰や文化を伝える役割を担っています。それぞれの神社に奉納された神馬には、固有の伝承や背景があります。神馬とともに守られてきた神社を訪れることで、歴史や文化への理解を深めることができます。
神馬がいる神社を訪れる際には、その姿だけでなく、神社が歩んできた歴史や地域との結びつきにも注目してみてください。きっとその場所が持つ特別な魅力を感じられるでしょう。
絵馬の由来と神馬のつながり


神社でよく見かける絵馬は、神馬と深い関わりを持つ日本の伝統文化の一つです。絵馬が奉納されるようになった背景には、古代から続く神馬への信仰と祈願の習慣があります。
神馬を奉納する古代の風習


古代日本では、神様の使者や乗り物とされる神馬が、重要な神事において奉納されていました。特に、農耕文化が発達した時代には、雨乞いや豊作を祈願するために黒馬や白馬が神社に捧げられることが一般的でした。しかし、実際に生きた馬を奉納することは大変な負担を伴うため、次第に木彫りの馬や馬の絵が代わりに使われるようになりました。
絵馬の起源と発展


生きた神馬に代わるものとして奉納された絵馬は、次第に装飾が施され、祈願の象徴としての役割を持つようになりました。室町時代以降、絵馬の大きさが大型化し、複数の人が共同で奉納するようになったことで、絵馬殿が神社に設置されるようになりました。これにより、絵馬は個人の祈りだけでなく、地域全体の信仰を表す存在となりました。
- 絵馬に見る神馬の名残
現在の絵馬にも、馬の姿が描かれているものが多く見られます。これは、絵馬が神馬の象徴として発展してきた歴史を反映しています。例えば、丹生川上神社では、黒馬や白馬に関連するデザインが取り入れられた絵馬が奉納されています。これにより、参拝者は神馬とのつながりを感じながら祈願を行うことができます。
- 絵馬がもつスピリチュアルな意味
絵馬は、祈りを神様に届ける媒体としての役割を果たしています。その起源にある神馬の神聖さは、絵馬を通じて現代でも引き継がれています。絵馬を奉納することで、古代から続く神馬への感謝や祈りの心を表すことができるのです。
絵馬の由来を知ることで、神社で行う祈願がより深い意味を持つものとなります。訪れる神社で絵馬を見つけた際には、その背景にある神馬とのつながりにも思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。
まとめ
- 神馬とは神様の使者や乗り物として信仰されてきた存在
- 神馬は古代日本の神事や儀式に欠かせない重要な役割を担う
- 東京では神田明神でポニーの神幸号に会うことができる
- 伊勢神宮の神馬は皇室から献上される由緒ある存在
- 白馬は雨乞いや晴天祈願の象徴として使用されてきた
- 日光東照宮ではニュージーランドから奉納された白馬がいる
- 神馬は地域の伝統行事に深く結びつき役割を果たしている
- 絵馬の起源は生きた神馬を奉納する代わりとして始まった
- 多度大社の神馬会は地域の支援で神馬を守っている
- 上賀茂神社では元競走馬が神馬として活躍している
- 丹生川上神社では黒馬と白馬が天候祈願の神事に使われる
- 神馬が登場する神社では日本の自然信仰の象徴が感じられる
- 神馬の像や絵は神社の守護としての役割も担っている
- 神馬は神社の歴史や地域文化を伝える象徴として重要である
- 神馬に触れることで日本の伝統文化を体感する機会が得られる




コメント