神社で行う結婚式は、大正天皇の御婚儀が始まりとされています。
一般には、明治時代になってから、現在のような形式での神前結婚式が広く昔及するようになりました。
ここでは、「神社検定テキスト 神社のいろは」第4章の53神神前結婚式について教えてくださいのページの内容を掘り下げて学習し、暗記しやすいようにスマホでも見やすい1ページにまとめてみました。
神前結婚式は、当時皇太子だった大正天皇のご婚儀が行われたことにはじまります。
明治時代になると、現在の神社で行われているような形式での神前結婚式が一般にも広く昔及するようになっていきました。
神前結婚式
神前結婚式は、明治33年5月10日4月に当時の皇太子殿下(大正天皇)と九条節子様(貞明皇后)の結婚式により始まったとされています。
皇居内の賢所(かしこどころ)に於いて、皇室婚嫁令に基づいて結婚式が行われました。

この後、民間での神前桔婚式への関心が高まりました。
翌年、日比谷大神宮(現東京大神宮)に於いて、ご婚儀のご慶事を記念して皇太子のご婚儀にならって公開で神前模擬結婚式が行われました。
それ以前の一般の人の結婚式は家庭で行うことがほとんどでしたので、厳粛かつ神聖な神社のご神前で結婚の儀式を行うことは画期的なできごとでした。
それまでの結婚式は「結婚は神のお計らいであり、恵みである」という古くからの信仰のもと家庭で行われていました。
江戸時代に確立され、公家や大名はじめ、武士や庶民にまで広かっていたようです。
床の間に伊弉諾尊と伊弉冉尊を祀り神饌をお供えして行われていました。
こうして人々の関心を集め、その後は一般人の結婚式が同神宮で行われるようになりました。
大正元年に発表された夏目漱石の小説『行人』にも、結婚式の様子が描かれています。
これが土台となり、神社での神前結婚式は広く受け入れられ、一般的になったのは昭和20年代以降です。

戦後の住宅事情、食糧事情から自宅での式が困難だったためとも考えられます。
高度成長期に入ってからは地方でも都市化が進み、神前結婚式が多く行われるようになっていきました。
三献の儀 三三九度
神前結婚式の特徴は、「三献の儀」です。「三三九度」とも呼ばれています。
お神酒を一杯飲むことを一度、三度飲むことを一献とし、これを三献、つまり九度いただく作法のことをいいます。
これは、平安時代の公家の酒宴の作法とされたものですが、男子の成人を祝う元服などの儀式でも行われていました。
【三献の儀】
一献目「新郎→新婦→新郎」
二献目「新婦→新郎→新婦」
三献目「新郎→新婦→新郎」
このような順番でつがれていくのが丁寧な作法とされています。
現在の結婚式では、省略されており短くなっている場合があります。
一献目「新郎→新婦」
二献目「新婦→新郎」
三献目「新郎→新婦」

神前結婚式 式次第
神前結婚式の式次第は一般のお祭りの流れとほぼ同じです。
- 修祓
- 斎主一拝
- 献餞
- 祝詞奏上
- 三献の儀
- 誓詞(せいし)
- 玉串拝礼
- 親族杯の儀
- 撤饌
- 斎主一拝

神前結婚式についての問題です
これまでの神社検定試験で実際に出題された過去の問題です。
神社検定試験過去問題集に記載されたものを選んでみました。
問題1

神前結婚式は、あることがきっかけで明治以降に広く普及するようになりました。そのきっかけとは何でしょうか。
- 有名芸能人が神社で行った
- 皇室のご婚儀
- 有名作家が神社で行った
- 大ヒット小説の中で描かれた

答えは2 皇室の婚儀
過去の試験での出題
- 平成24年6月3日 第1回神社検定 問36
神前結婚式についての10問クイズ
初級編(簡単な問題)
- 神前結婚式とはどのような形で行われる結婚式ですか?
A) 神社の神様に結婚の報告と加護を祈願する伝統的な式
B) 教会で神父の前で行う結婚式
C) 市役所で行う婚姻届提出の儀式
D) 海外で行うリゾートウェディング
答え: A) 神社の神様に結婚の報告と加護を祈願する伝統的な式 - 神前結婚式が広まるきっかけとなった歴史的な出来事は何ですか?
A) 明治天皇の結婚式が神前で行われたこと
B) 江戸時代の武家婚礼の普及
C) 昭和時代の海外文化の影響
D) 平安時代の貴族の結婚儀式
答え: A) 明治天皇の結婚式が神前で行われたこと - 神前結婚式で新郎新婦が着用する一般的な服装は何ですか?
A) 和装(紋付袴と白無垢)
B) 洋装(タキシードとウェディングドレス)
C) カジュアルな私服
D) スポーツウェア
答え: A) 和装(紋付袴と白無垢)
中級編(少し難しい問題)
- 神前結婚式の中で、三三九度(さんさんくど)とはどのような儀式ですか?
A) 新郎新婦が酒を交わして夫婦の絆を深める儀式
B) 両家の親族が挨拶を交わす儀式
C) 神職が祝詞を奏上する儀式
D) 神社の拝殿で参拝する儀式
答え: A) 新郎新婦が酒を交わして夫婦の絆を深める儀式 - 神前結婚式において、神職が新郎新婦に授ける「玉串(たまぐし)」の意味は何ですか?
A) 神様への祈りと感謝を込めた供え物
B) 結婚の証明書
C) 両家の交流を象徴する記念品
D) 新しい命を祝福する飾り
答え: A) 神様への祈りと感謝を込めた供え物 - 神前結婚式で重要な「祝詞奏上(のりとそうじょう)」とはどのような内容ですか?
A) 神職が新郎新婦の結婚を神に報告し、加護を祈願する言葉
B) 新郎新婦が親族に結婚の決意を伝える言葉
C) 両家の親が交わす誓いの言葉
D) 参列者が新郎新婦に送る祝辞
答え: A) 神職が新郎新婦の結婚を神に報告し、加護を祈願する言葉
上級編(難しい問題)
- 神前結婚式で両家の親族が行う「親族杯の儀(しんぞくはいのぎ)」の目的として正しいものはどれですか?
A) 両家の絆を深め、家族としての結びつきを確認するため
B) 神職に感謝を示すため
C) 新郎新婦の将来の繁栄を祈るため
D) 神社に寄付を行うため
答え: A) 両家の絆を深め、家族としての結びつきを確認するため - 神前結婚式が神社の本殿ではなく拝殿で行われる理由として正しいものはどれですか?
A) 本殿は神聖な場所であり、神職以外が入ることが許されないため
B) 拝殿の方が収容人数が多いから
C) 神社の規模によって異なるため
D) 神前結婚式専用の場所が拝殿であるため
答え: A) 本殿は神聖な場所であり、神職以外が入ることが許されないため - 神前結婚式で新郎新婦が誓いの言葉を述べる場面を何と呼びますか?
A) 誓詞奉読(せいしほうどく)
B) 祝詞奏上(のりとそうじょう)
C) 献饌の儀(けんせんのぎ)
D) 神前参拝(しんぜんさんぱい)
答え: A) 誓詞奉読(せいしほうどく)
超難関編(非常に難しい問題)
- 神前結婚式が日本の伝統文化として注目される理由として最も適切なものはどれですか?
A) 神道の教えに基づき、結婚を社会的・宗教的に祝福する形式だから
B) 明治天皇が提唱した特別な結婚の形式だから
C) 武士の婚礼文化をそのまま受け継いだから
D) すべての宗教が統一された祝福形式だから
答え: A) 神道の教えに基づき、結婚を社会的・宗教的に祝福する形式だから


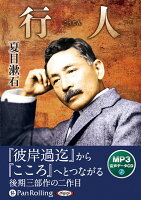



コメント